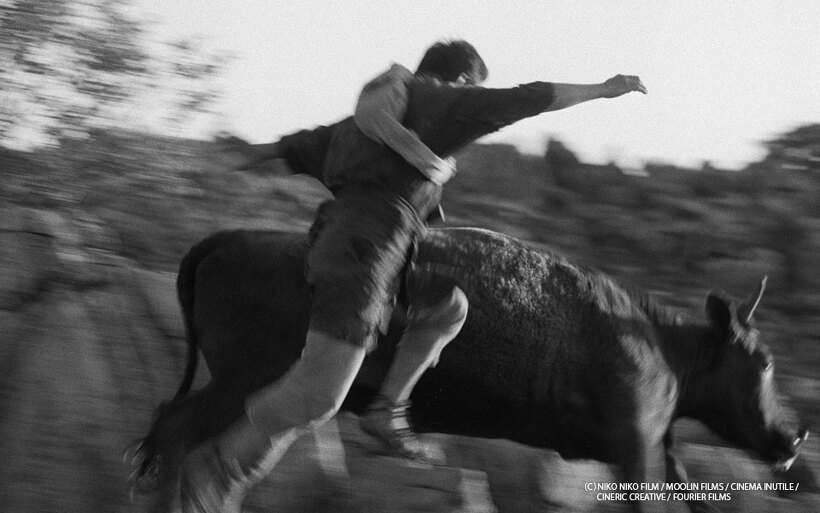富山県を舞台に作品を作り続けた
新進気鋭の坂本欣弘監督最新作
富山県の立山で3年に一度行われる女人救済の儀式「布橋灌頂会(ぬのばしかんじょうえ) 」をモチーフに、心に深い傷を負ったひとりの女性の再生と、新たな一歩を踏み出していく姿を描いたドラマ。
主人公・由起子を渡辺真起子、彼女と行動を共にする少女・ 沙梨を、ドラマ『なんで私が神説教』に出演し本作が長編映画デビュー作となる陣野小和が演じる。そのほか木竜麻生、室井滋らが出演。監督は、軽度の知的障がいのある女性の初恋を描いた『真白の恋』(17)、人生に立ち止まってしまった若者を手助けする場所に集う人々を描いた『もみの家』(20)など、一貫して自身の出身地である富山県を舞台に、その美しい風景と共に人々が抱える痛みとその癒しを丹念に映し出し、映画ファンの心を掴んできた坂本欣弘。
2025年製作/94分/G/日本
配給:ラビットハウス
あらすじ
15年前、3歳だった愛娘を亡くした由起子は、心に癒えぬ傷を背負いながら、今もその罪の意識から逃れられずにいた。ある日、とある絵画を偶然目にして心を奪われた彼女は、駆り立てられるように、その絵が描く舞台の地へと足を運ぶ。立山連峰を望む橋のたもと。様々な想いを抱えた女性が集うその場所で、由起子は不思議なひとときを過ごすことになるのだった。
解説
空疎な日々に光を灯す
ひとときの空流
本作は、現在でも3年に一度、実際に富山県の立山で催される女人救済の儀式「布橋灌頂会(ぬのばしかんじょうえ)」をモチーフにした作品。心に深い傷を負い、自責の念にかられたひとりの女性が導かれるように「布橋灌頂会」に参加し、その後、立山で出会った様々な人々、様々な出来事を通じて、いかにして新たな一歩を踏み出せたのかを描いた物語。主演は、1998年に映画『バカヤロー!私、怒ってます』で俳優デビューを果たして以降、日本映画界を支え、牽引し続けてきた渡辺真起子。立山で育ち「布橋灌頂会」の手伝いをしていたことをきっかけに由起子と出会い、行動を共にすることになる少女・沙梨役には、2025年に日本テレビ 土曜ドラマ『なんで私が神説教』に出演した他、CMでも活躍し、本作が長編映画デビュー作となる陣野小和。由起子と共に「布橋灌頂会」に参加したことをきっかけに奇妙な巡りあわせにより由起子と沙梨と関わり合いを持つ夏葉役には、カンヌ国際映画祭監督週間に出品された『見はらし世代』(団塚唯我監督)に出演した木竜麻生。そして、由起子の過去を知り彼女に優しく寄り添う美佐江役には富山県出身の俳優、室井滋が扮し、個性豊かな俳優陣が脇を固めます。
布橋灌頂会(ぬのばしかんじょうえ)
江戸時代、生前自らが積み上げた罪によって、死後、地獄に堕ちると信じられていた。この不安から逃れるために、男性の間で罪滅ぼしを目的とする「立山禅定登拝」が盛んになった。一方、女性は死後必ず地獄に堕ちるとされ、立山への登拝も許されていなかった。極楽往生を願う女性たちを救うため、閻魔堂・布橋・うば堂を舞台に行われたのが「布橋灌頂会」(布橋大灌頂)。明治期になると、神仏分離や女人禁制が廃止された影響もあり、布橋灌頂会も行われなくなった。平成8年(1996)に現代的なイベントとして復元され、近年は3年に一度、開催されている。
オフィシャルサイトはこちら >>